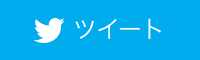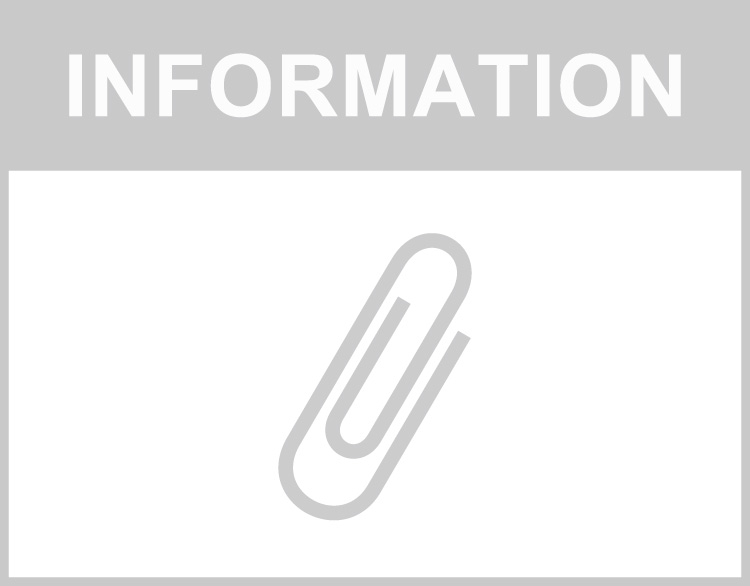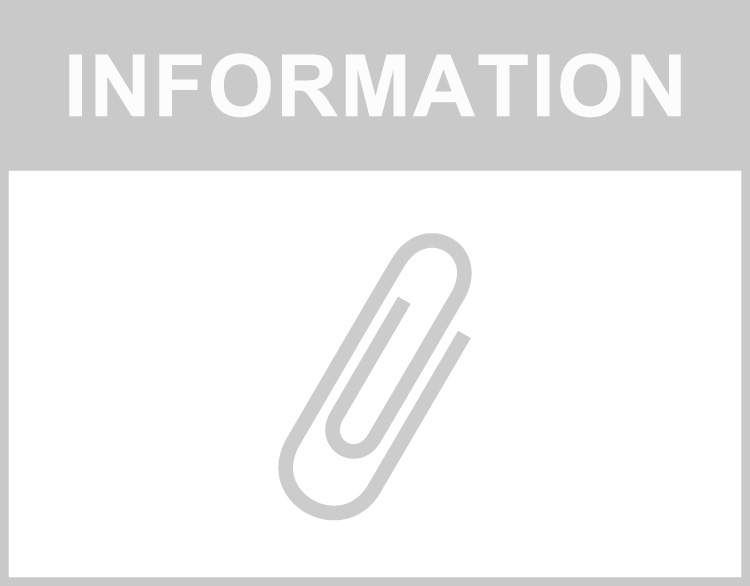【インタビュー】走墨の世界 増永広春先生

全身にみなぎるエネルギーを筆に託し、墨を走らせ、イマジネーションをぶつける。
書家・増永広春さん。自身のオリジナルである「走墨(そうぼく)」の世界は、伝統とモダンの融合美です。
このたび、増永広春先生にインタビューを行いました。
書との出会いから「走墨」が生まれるまで、日々のこと、などお聞きしました。

■書道との出会いを教えてください。
小学校に上がる前くらいでしょうか。
母のそばで筆をおもちゃにしてよく遊んでいました。らくがきをして叱られた思い出もあります。
母は専業主婦でした。父の仕事の手伝いで、代筆をしたり、年賀状や手紙を書いていました。
着物を着て、しょっちゅうこの二月堂で手紙を書いていました。
私が学校を休むとき、"今日は休みです"と伝言を書いて友達に持って行ってもらうと、その字が上手すぎて読めないと言われるほどで。
「あなたのうちのお母さんはすごいね」と言われ、それが自慢でした。

お母様から譲り受けた二月堂をお教室にも持ち込んで
■絵を描くことも好きだったのでしょうか。
書を始めてから勉強会に参加して習いました。
クロッキーから始めて、"ぱぱっと描く"ということをデッサン教室で学びました。
書を書き進める中で、何か他の世界、ちょっと違う方向性、自分の世界でやっていきたい。という思いがありました。
お花、お茶、織物、陶芸など別の世界も挑戦した中で、最終的に書道を選んだというわけです。

増永先生のスケッチ画
■その後の作品制作、広がりについて
デッサン教室に通うころ、ワルシャワ美術館のドローイング展に出展する機会がありました。
するとその作品がすぐ買取になり、ラフスケッチも、墨で書いたものも売れてしまいました。
日本人ではなくドイツ人に買ってもらえたのです。
それが大きな自信となりました。
その後は、書道をしながら絵を描いて、自分だけの作品を作っていきました。
あるとき、銀座松坂屋で文字の作品展を開きました。
そこに当時電通にいらしたディレクターの方がふらりと入ってきて、「君、こんなポスターがあるんだけど書いてくれる?」と、
自転車の写真を見せられ相談されました。
ぜひ引き受けたくて、1週間くらい経って見せに行ったところ、
「どうしてこんなの描けるの、芸大の人だって、誰も描けないよ」と驚かれました。
そこから日本自転車振興会の仕事が20年続きます。
その作品が世の中に広がって、"筆で描く人"という認識が広がり、
長野冬季オリンピックのIBMポスターなど、さまざまな仕事がきたのです。
スポーツする人、動いている人、というモチーフは、元々は自転車がきっかけだったのです。
そこから相撲、柔道、野球なども描きました。
何一つ断わることなく、何でも引き受けました。結果的にそれがすごく勉強になったと思います。
母が元気なころには墨をたくさん買ってくれ、応援してくれていました。
紙や筆にはお金をすいぶん遣いましたが、それが今に活きています。
■「走墨(そうぼく)」の始まり
人間の生命の動きを捉えたい。という思いがありました。
中国の書も勉強しながら、新しい世界を作ろうと、書と絵画の融合「走墨(そうぼく)」をオリジナルで始めました。
今から30年以上前のことです。
「もっと自分のスタイルを打ち出したら」と言ってくれた友人がいて、そこから「走墨」が生まれたのです。
にじみ、エネルギッシュな線、強弱を付けて描く、ということで肉体の生命観を出していきます。
そういうものを深く深く探求してきたのが「走墨」です。

絵の本も出版し、とても勉強になりました。
掛け軸ひとつにしても、空間の美しさや、1枚の絵がいかに空間に活きるか、ということを考えて。とても勉強になります。
このようにしていろんなことをやって、最終的に今につながっています。
広春の走墨は、「なんとかしなくちゃ、これでおわりたくない」というのがずっと根底にあるんです。

■スポーツの絵をたくさん描かれていますが、先生もスポーツをされるのですか。
若い頃は何でもやりましたよ。
スキーはカナダまで行って滑ったり、ゴルフコンペも主催したり。
ずいぶんお金も遣ってきました。そういう時代だったんです。無駄遣いもいいんですよ、活きるんですよ。
今はピラティスをやっています。週1回、先生に付いてしっかり1時間。ストレッチをしたり、スポーツクラブに行ったり。
書道は毎日座っていて足も縮んでしまうので、身体を伸ばさないといけません。
そのおかげで身体の調子はとてもいいです。
自分でスポーツをしていないと、なかなかあのような身体の動きは捉えられませんし、難しいものです。
■創作の日の流れを教えてください。
今日は描くぞ。という日があります。
今日は散歩に行く。という描かない日もあります。
考えがまとまったとき、描きます。前日に、明日は描こう、と決めてお昼からやって夜までに仕上げる、という予定を決めます。
そして集中します。

先生がご自宅で使われている いつもの文房具
だいたい土曜や日曜の、静かな日に描きます。たとえば土曜日は外に出て美術館に行こうとしても混むので、
平日に美術館に行ったり、人の書を見に行ったりしています。最近はインターネットで作品を調べたりもしますよ。
女流書道家の篠田桃紅(しのだとうこう)先生の展覧会は必ず行きます。精神力の強い方で、すばらしい書を書く人です。
その先生に若い頃に就きたいと思いましたが、弟子を取っていませんでした。
ニューヨークでずいぶん活躍されて、今も書いていらっしゃって世界中に作品があります。
線なのか文字なのか、という少し抽象的な、平安かなを現代的に書いている方です。
■ご自宅で描かれるときはどのようにしていますか。
マンションの中で、机ではなく、床で書いています。
あまり耳に強くないような音楽をかけることもあります。クラシックではなく、サラブライトマン、タンドゥン、中国の古い民族音楽、など。
真剣には聞かないけれど、静かに、何にもないよりは。という感じです。
筆は毎日持ちます。
手紙でも作品でも。筆を持たない日はありません。

旅には使いきりの筆ペンを持っていきます。
旅先では、街で見つけた植物を筆にしたり、旅館の食堂でランチョンマットに
ちょこっと書いてプレゼントして帰ったり、ということも。
■使っている筆について
筆はずいぶんあちこちから買い集め、あれこれ試しました。数えきれません。
今使っているのは練馬に住んでいる伝統工芸作家の方の筆。今はこれだけです。やっぱり全然違うのです。材料が違うのでしょうか。
筆屋さんが、私がライブパフォーマンスをしているときに見に来てくれます。私がどういう風に描いているのかを見ているのです。
相撲の絵を描くとき、使っている実際の動きを見てもっと強い筆に改良しなければ、と思ったそうです。

作品制作に使われている、こだわりの筆
■ひとつの作品を作り上げるまで
一つの作品制作で使う筆は1本です。ほとんど1本で描きます。持ち替えるのは気合いの入り方が違うかなと思い、持ち替えません。
描くまでには長く長く考えるけれど、描き始めたら速いですよ。
何を描くにしても、あっという間、という感じです。"富士山"という文字だって2分くらいでしょうか。考える時間が大切なのです。
考えるのは数日間。そして最終的に自分の気持ちをぶつけていきます。
制作をするときには、小さな部屋で大きなことを考えます。
広いところで考えると、なんとなく広がってしまって、散漫になります。今までいろいろなことをやってきて、
いろいろな場所に行き、大きいところでも描きましたが、小さいところ、狭いところの方が大きく描けるんです。
■作品として描くことがつらくなる時や、スランプはないのでしょうか。
ありますよ。ちょっと違うことをやっていることでひがまれたり。めちゃくちゃに言われたりするからこそ、がんばれます。
世の中に出ていけば、出ていくほど、そういうこともありました。
そんな時、「もう少しがんばっちゃうよ!」という、それくらいの気持ちになるんです。
自分で新しい作品を作ったり書いたりすることで黙らせる。いちいち気にしていてはできないですから。
言われてもいい、黙って聞いているから。
それが「ぶつける」ということです。

■今現在の活動について教えてください。
海外からいらっしゃる方への講座を持っています。
筆を持ったことのない方にも、手を添えて教えます。まさに手取り足とり。
最初は一人二人でしたが、いろいろな提案をしていったらどんどん受講者が増えています。

この日はアメリカから20名ほど
皆さん本当に楽しそうに書かれるんです。
平安貴族はこんな風にしてラブレターを書いた、と言って「いろはにほへと」を教えたり。
話が広がり、リクエストをもらって描きます。「なんでも言ってちょうだい。」と言って。
1クラス2時間。興味がない人もいるし、次々に質問ばかりする人もいるし、
みんな同じじゃないから面白いんです。お客様はみんな違うから、みんな違う字になります。
もう世界中の2千人くらいの人に教えたことになります。参加した人たちが情報を流してくだり何回も来て下さって広がっていきました。
こういった公開講座は今は外国人の方へのみです。
海外の皆さんに会うと、日本のこういう世界が大好きなことにびっくりします。どれをとっても驚かれます。
カルチャーショックを受けているようです。墨を摺っているだけで写真や動画をたくさん撮ってくださって。
6年ほど前、アルジェリアに一人で行く機会がありました。
外務省からアルジェリア独立50周年の仕事で、文化交流をしてほしいということでした。
アラビア語と、向こうのデザイナーとジョイントして、現地の書道美術館に80点くらい持って行きました。一人でかついで行きましたよ。
文字、自然、人間、スポーツ... 宮殿の中で1ヶ月くらい展示してくださいました。
1週間の滞在中、あちこちで書を書き、差し上げました。
現地の方は帯も着物も気になって、墨も珍しくて、何でも欲しがります。見たことがないからですね。
ホテルの中を歩いていると、「あなたをテレビを見たよ」と声をかけられたり。
なので、海外に行くときは必ず着物を持っていきます。お土産に大使館に置いてきたこともあります。
どんなところに出て行くときも気持ちに余裕がないといけません。
そういうふうにやっていくんだ。と、観念して臨むのです。
■現在は外国人の生徒さんが多いようですが、日本の方にも教えているのですか。
日本の方にも別で教室を持っています。書道に加えて「走墨」も、やさしいものを教えています。
書道は習えても走墨は難しい。基本ができていないとできないのです。絵も描けないといけないので。
それでも「走墨」を習いたいという人は多いです。
今はパソコンでなんでも済ませてしまっているから、お習字を勉強しよう、書道をやりたい、という人は多くないと思います。
皆さん時間がないのでしょうね。
私の講座は、墨汁は使いません。墨が絶対です。
書は、中国から来て、日本の文化となり、今世界に向けて新しい一歩を切り開いています。墨絵でもない、絵画でもない、新しいものを作っています。
日本の伝統的な筆を使い、全部自然のものを使って。墨、筆、紙。全部土に還るものです。
■銀座との関わりについて
私は元々銀座にいました。当時の松坂屋の裏(6丁目)あたりにアトリエがあり、14年間そこで仕事をしていました。
伊東屋さんにもしょっちゅう行きましたよ。銀座でお教室をやったりと、当時は優雅な感じでした。銀座は大好きな街です。
お蕎麦屋さんの「笑笑庵(しょうしょうあん)」(銀座2-10-18)とのつながりも20年くらいです。
ある日、「笑笑庵」を作るにあたって、書道家がいないかと担当の方がタウンページを見て尋ねてきました。
「明日オープンだからパーティー出席者の名札を筆で書いて欲しい」と言われました。
全員分書いて、受け取りにいらしたときにお代を聞かれましたが、「いただけないです、お祝いですよ」と言ったんです。
そのうちに食べに伺います、と言って別れました。そしたら、「笑笑庵」の看板を書いてほしい、と言ってきたんです。


「笑笑庵」入口の看板。お店の中にも先生の作品が展示されています
また、うどん屋さん「つるとんたん」の銀座のお店にも、絵があります。それはずいぶん昔にお相撲の絵を描いた会社のつながりでした。
※「つるとんたん 銀座店」(銀座東急プラザ10階)の個室では先生の作品が見られます。
どこにご縁があるかなんてわからないものです。

「つるとんたん 銀座店」の個室
■今後の活動と、もっとこういうことをやってみたい、ということはありますか。
この後は、イベントがあったり、頼まれてライブをする予定があります。来年あたりは世界に行くこともありそうです。
内に秘めて考えていることはそれほどないのですが、「本物を知って欲しい」ということでしょうか。
年季の入った、"らくがき"にならないもの、です。
こころの叫びというのは年季がはいっていないとなかなか伝わらないんじゃないかと思います。
場をたくさん踏んで、中身の濃いものを示して、見る人を感動させたいと思います。
世界で皆がやっていない、見たことのないものを見せたい。
そういう意味では、銀座のあの場所で行うのは、また新しいステップができるかもしれないですね。